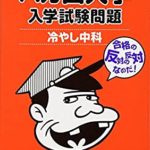京都大学はじめ、難関大学を目指す受験生の皆さん!
「青チャート」や、「一対一対応の数学」など、基礎的な参考書を終えて、次に何をしようか考えている人、多いのではないでしょうか?
そこで今回の記事では、「世界一わかりやすい京大の数学合格講座」に関する、正しい使用方法につて解説していこうと思います!
世界一わかりやすい京大の数学合格講座の正しい使い方
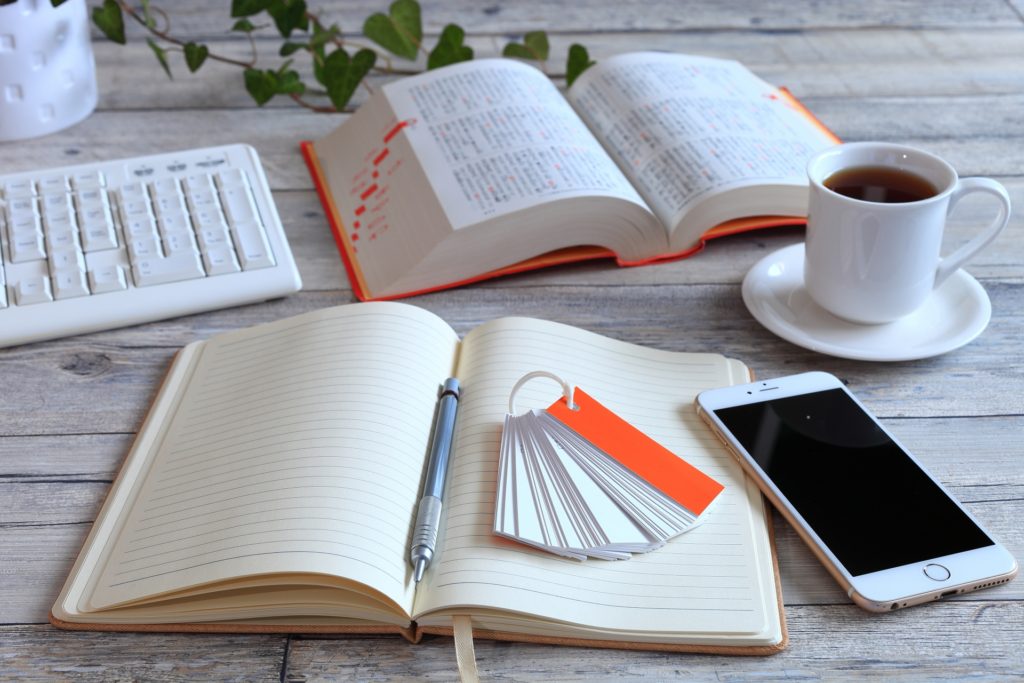
どのような内容?
この参考書は、名前の通り「京都大学」を目指す受験生向けの参考書として作られていますが、京都大学以外の難関大学を目指す受験生にもおすすめの参考書となっています!
この参考書の特徴は、何と言っても、その解説の豊富さです。
多くの数学の参考書は解答が付いているだけで、その解答に至る考え方等は書かれていません。
しかし、この参考書は違います!
1問に対して、3ページ以上もの優れた解説がついており、解答へと至るためのプロセスが事細かに書かれています。
掲載されている問題は、京都大学の過去問などと言った非常に難しいものですが、この詳しい解説により、深く理解できるようになっています。
いつくらいから、やればいい?
「世界一わかりやすい京大の数学合格講座」は、「青チャート」や「一対一対応」などと言った基礎的な参考書を終えた後に、使用されることが想定されています。
基礎が終わっていないと、手も足も出ないと思うので、先に基礎力をつけてから取り組まなければいけません!
また、京都大学志望の人に対しては、過去問や「25か年」への導入としても非常に優秀です。
時期としては、夏休み中~夏休み後あたりから、1か月~2か月を目処に取り組めるのがベストでしょう。
共通テスト後は、過去問に集中的に取り組んでいきたいので、遅くても10月頃には取り組み始めるべきだと思います!!!
どのように取り組めばいい?
次は、実際に「世界一わかりやすい京大の数学合格講座」に、どのように取り組んでいけばいいのか、について解説していきます。
上でも言った通り、この参考書に収録されている問題の多くは、京都大学の過去問で構成されています。
そのため、分からなかったらすぐに解答を見て、それを覚えながら進めていくという方法はおススメできません。
それをやってしまうと、せっかくの過去問が無駄になってしまうからです。
過去問というのは、その大学に合格するための最も重要なヒントとなる問題です。
なので、まずは何分かかってもいいので、しっかりと考えてみましょう!
(最低でも30分はしっかりと考えてみてください。)
その後、解説をしっかりと読み込み、「自分の解答の方向性はあっているのか?」「どこでミスをしたか?」「抜けている記述はないか?」などを検討していってください。
まとめ
いかがでしょうか?
今回の記事では、「世界一わかりやすい京大の数学合格講座」の正しい使い方について、解説していきました。
ぜひ、この記事を参考に、合格目指して頑張っていきましょう!
また他にも、受験勉強に役立つ情報をたくさん配信しているので、チェックしてみてください!
この記事はここで終了です。
最後まで読んでいただきありがとうございました!